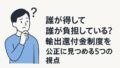2020年代に入り、日本でも「父親が家事や育児をするのは当たり前」という価値観が広がりつつあります。共働きが当たり前になった今、家庭内の役割分担の見直しが進んでいます。
しかし、その一方で、家事や育児に参加し始めた父親たちが新たな課題や葛藤を抱えている現実も見逃せません。
この記事では、日本における父親の家事参加の現状と直面する課題、それに対する対応策を解説。さらに、アメリカ・中国・マレーシア・韓国の家事参加状況と比較しながら、これからの「家族のかたち」について考えていきます。
日本の父親たちが家事に関わるようになった背景
• 「イクメン」ブームの浸透
• 共働き世帯の増加
• 法制度の後押し(産後パパ育休など)
• 家族観の変化
例えば、総務省の「社会生活基本調査(2021年)」によれば、男性の家事・育児への参加時間は20年前と比べて約20分増加しています。しかし、同調査では女性の家事育児時間が平均7時間を超えている一方で、男性は1〜2時間前後にとどまっており、依然として格差は大きいのが現実です。
また、国立成育医療研究センターによる「子育て世代包括支援に関する調査」(2022年)では、父親の4割以上が「育児に不安を感じている」と回答。育児への参加が進んでいるからこそ、戸惑いや悩みを抱える父親も増えています。
日本の父親が直面している4つのリアルな課題とその対策
1. 心理的負担と「ちゃんとできているか不安」
慣れない家事や育児をこなすなかで「ちゃんとできてるのかな?」と不安に思ったり、「やってるつもりなのに感謝されない…」とモヤモヤすることも。SNS上では「#育児ノイローゼ」「#ワンオペ育児」といったワードも多く見られ、父親自身が孤立するケースも報告されています。
対策:
• パートナーとの“気持ちの共有”を習慣にする
• 「全部やろうとしない」「手を抜く家事」を許可する
• 自治体のパパ向け育児講座やオンラインコミュニティでつながる
• 育児・家事に関する情報源(本・ブログ・ポッドキャストなど)を日常的にチェック
2. 職場の理解が追いついていない
育児休業や時短勤務などの制度が整備されつつある一方で、実際に使える雰囲気がない職場も多く、「名ばかり制度」になっているケースも。
対策:
• 上司や同僚に“家庭の事情”を正直に共有する
• 育児休業の取得希望は早めに伝える(2〜3か月前が理想)
• 社内制度や福利厚生をしっかり調べて活用する
• 企業の「イクボス」推進事例を社内に紹介してみるのも一案
ポイント:「制度は“使ってこそ”意味がある」
3. 夫婦間の“やってるつもり”ギャップ
「夫はやってるつもり」「妻は足りないと感じる」このすれ違いは非常に多いです。これはタスクの“見えにくさ”と“期待値の違い”が原因です。
よくある例:
• 妻「言わないとやらない」
• 夫「言ってくれたらやるのに」
対策:
• 家事・育児の“見える化”をしてタスク表を共有する
• 「ありがとう」「助かったよ」をお互い伝える
• 手順が違ってもOK!相手のやり方を認める柔軟さを
• 定期的な“家庭内作戦会議”で分担のアップデート
4. 親世代との価値観ギャップ
親世代は「家事は女性がやるもの」「男は仕事を頑張ればOK」という価値観で育っているため、どうしても衝突が起きやすくなります。
対策:
• 最新の育児方針を丁寧に説明(育児書や自治体資料を活用)
• 祖父母にお願いするルールを夫婦で共有し、伝える
• 感謝を忘れず、協力スタンスは崩さない
• どうしても価値観が合わない場合は「距離を取る勇気」も大事
ヒント:「親世代は“知らないだけ”のことも多い」
海外の父親たちはどうしてる?4カ国比較
アメリカ:柔軟な夫婦スタイルと課題の“見えにくさ”
• 週末だけでなく平日も育児を“シェア”する夫婦が多い
• 外部サービス(ベビーシッター、家事代行)を活用するのが一般的
• 国としての育休制度は未整備だが、企業レベルでサポートが充実している場合もある
日本との違い:夫婦で役割分担をする意識が強く、祖父母は関与しない家庭も多い
中国:共働き社会と“祖父母の力”
• 都市部では共働き率が高く、女性も高学歴・高収入が当たり前
• 祖父母(特に母方)が育児を担う割合が高い
• 父親の育休制度は地域によって差がある(5〜15日程度)
日本との違い:家事・育児のアウトソーシングより“家族ネットワーク”で乗り越える
マレーシア:家事を“外注する”スタイル
• 住み込みメイド文化があり、家事を外部に任せるのが一般的
• 共働きが増えている一方で、男性の家事参加はやや限定的
• 父親の法定育休(7日間)は最近導入されたばかり
日本との違い:“全部自分たちでやる”という発想はあまりない
韓国:日本に似た課題と急成長する育休制度
• 育児休業取得者に占める男性割合が30%を超える(2024年)
• 家父長制の影響が根強く、男性の家事時間はOECD最低レベル
• 若年層ほど「男女平等な家事分担」意識が強まっている
日本との違い:育休制度の普及は進んでいるが、実態の行動変容には時間がかかっている
日本が学べること、そして家庭でできること
• アメリカ:夫婦の会話と柔軟な外注スタイル
• 中国:祖父母や親族ネットワークを活かす方法
• マレーシア:家事育児のアウトソースという選択肢
• 韓国:政策の後押しで父親が家庭に関わる文化を形成中
どの国にも共通するのは、「夫婦がチームになること」「外部に頼る柔軟性を持つこと」
そして、日本でも少しずつ「家庭の中心に父親がいること」が当たり前になりつつあります。
おわりに:夫婦でつくる、わが家のチームプレイ
家事や育児は、“誰かが一人で抱えるもの”ではありません。
パートナー同士が思いやりを持って協力し合うことで、より豊かな家庭が築けます。
• 完璧じゃなくていい
• 小さなありがとうを忘れない
• 外部の力も借りていい
世界を見れば、家庭のかたちは一つじゃないことがわかります。
これから家族を築いていく皆さんにとって、この記事が少しでも参考になれば嬉しいです。
参考リンク・文献:
内閣府 男女共同参画白書 総務省 社会生活基本調査(2021年)
国立成育医療研究センター 父親支援に関する調査報告 OECD Gender Data Portal
マレーシアの父親の育児休暇制度に関する記事(NNA ASIA)