子どもが生まれると、家計は劇的に変化します。オムツ・ミルク・医療費・保育費……大人だけの生活とは違い、「今しかかからないけど、意外と負担が大きい支出」が一気に増えます。特に1人目の出産直後は、生活ペースもお金の流れも一変して、戸惑う人も多いはず。
とはいえ、ただ「節約しなきゃ…」と焦っても、ストレスがたまり長続きしません。
この記事では、小さな子どもがいるご家庭(1人目中心/兄弟がいる場合も含む)向けに、
• 目的別の節約スタイル
• 節約効果が出やすい支出項目ごとのテクニック
• 兄弟がいる家庭ならではの工夫
• 無理なく節約を続けるコツ
を、実例や平均支出の傾向も交えてご紹介します。
目次
節約は目的別に考えるのがコツ

節約とは、「ただ支出を減らすこと」ではなく、「目的のためにお金を整えること」。
家族によって目指すゴールは違います。だからこそ、まずは“自分たちの節約スタイル”を明確にすることが重要です。
1. 赤字を減らしたい【やりくり改善型】
• 出費の波が大きくて、毎月赤字ギリギリ…という家庭向け
• まずは“固定費”を見直すのが効果的
• クレジットカード払いの「見えない出費」を“見える化”するのが第一歩
2. 教育・将来の備えをつくりたい【将来準備型】
• 数年後の進学やマイホームを見据えて、コツコツ貯めたい
• 「先取り貯金」や「児童手当の全額貯金」など、“自動化”がポイント
• 無理な節約より“資産の仕組み化”を意識
3. 心と時間にゆとりを持ちたい【生活ゆとり型】
• 節約でイライラしたくない、時間も大事にしたい
• 手間をかけずに“自然に節約できる工夫”が中心
• 食材宅配や家電見直しなど、“先に整える”ことで負担軽減
節約しやすい支出項目と具体的な見直し方法
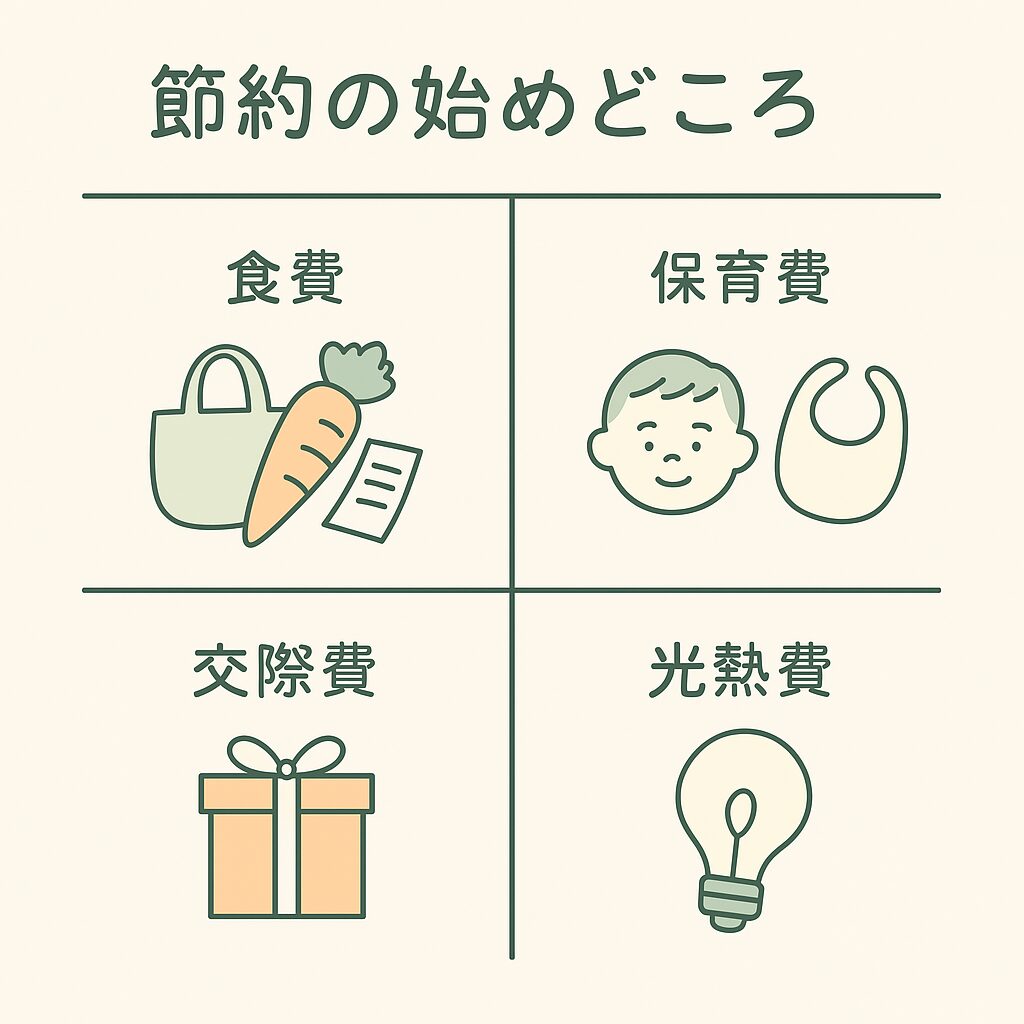
1. 食費(家計全体の約25〜30%)
【見直し効果:大】
• 買い物は“週1回”にまとめる(買う回数が多い=ムダ遣い増)
• 冷凍ストック&下味冷凍で時短&ロス削減
• ふるさと納税でお米・肉・離乳食系を確保
• **レトルトや冷凍食品は“疲れない日の味方”**として活用
子どもが食べない=作り直し=二重コストになりがちなので、
“食べきれる量・手抜き上等”で回すことが大切。
参考:総務省家計調査(2022)によると、4人世帯の平均食費は月約78,000円。
→目安より高ければ見直し余地あり。
2. 交際費・イベント費
【見直し効果:中〜大】
• 誕生日や季節イベントは「おうちパーティ+飾りつけ」で楽しむ
• ご祝儀やプレゼントは“気持ち+相場感”で充分(張り合わない)
• ママ友との付き合いは“1回の単価より回数”で調整
• 写真館はオフシーズン&ネット予約で節約
“交際費は減らす”よりも、“気持ちはそのままに、手段を変える”のがポイント。
3. 保育料・教育費
【見直し効果:大】
• 保育の無償化は0〜2歳でも条件によって対象(住民税非課税世帯など)
• 認可保育園/認定こども園を優先検討(認可外は補助金チェック)
• ベビーシッターの助成制度(自治体によって1時間500円など)
• 私立園でも“副食費だけ実費”のケースもあるので確認必須
一番大きな支出になる「教育費」。
0歳から制度を最大限活用するのが大事。
参考:全国平均で1人あたりの保育料は、月3〜4万円台がボリュームゾーン(認可園)。
4. 光熱費・通信費
【見直し効果:中】
• 電力・ガスの契約は“まとめて”見直す(セット割)
• エアコンは28℃+サーキュレーターで効率UP
• 夜間割・オール電化割などの時間帯を活かす
• 通信費は格安SIM+Wi-Fiの組み合わせに変更
冬・夏の電気代は、見直し効果が大きい。
契約そのものを変えるだけで年間1〜2万円の節約も。
5. 保険
【見直し効果:大(過剰契約が多いため)】
• 子どもは基本「医療費助成+乳児医療証」で自己負担ゼロの自治体が多数
• 医療保険よりも「入院時の生活補填が必要か」で判断
• 親の生命保険は“万が一”を最低限に
• 学資保険よりも“新NISA”の方が利便性高い
保険は一度入ったら見直しにくい。出産後の今こそ“今の家族構成で最適か”再チェックを。
6. 貯蓄・資産形成
【見直し効果:時間×習慣】
• 先取り貯金(定額を別口座へ自動振替)が基本中の基本
• 児童手当は“全額貯金 or 口座分け”が王道
• 新NISA(つみたて)/iDeCoで“勝手に増える仕組み”を作る
• 家計簿アプリ(マネーフォワード/Zaimなど)で可視化するだけでも◎
「貯まらない」は“仕組み化していない”のが原因。
“使っていいお金”を明確にすることで、精神的にも余裕ができる。
兄弟姉妹がいる・これから増える場合の工夫

お下がり文化を前向きに活用
• サイズ別にラベル収納、清潔・状態維持がコツ
• 思い出グッズは「1人1箱」ルールで絞る
育児用品の“買う基準”を変える
• ベビーカー/抱っこ紐/ハイチェアなどは、“耐久性・長期使用”を軸に選ぶ
• 高くても「2人目以降にも使える=結果的に割安」になることも
自治体制度の多子支援
• 2人目以降の保育料軽減・学用品支給など
• 所得制限は「前年度収入ベース」なので産休・育休中は有利に働くケースも
無理なく続けるための節約のコツ
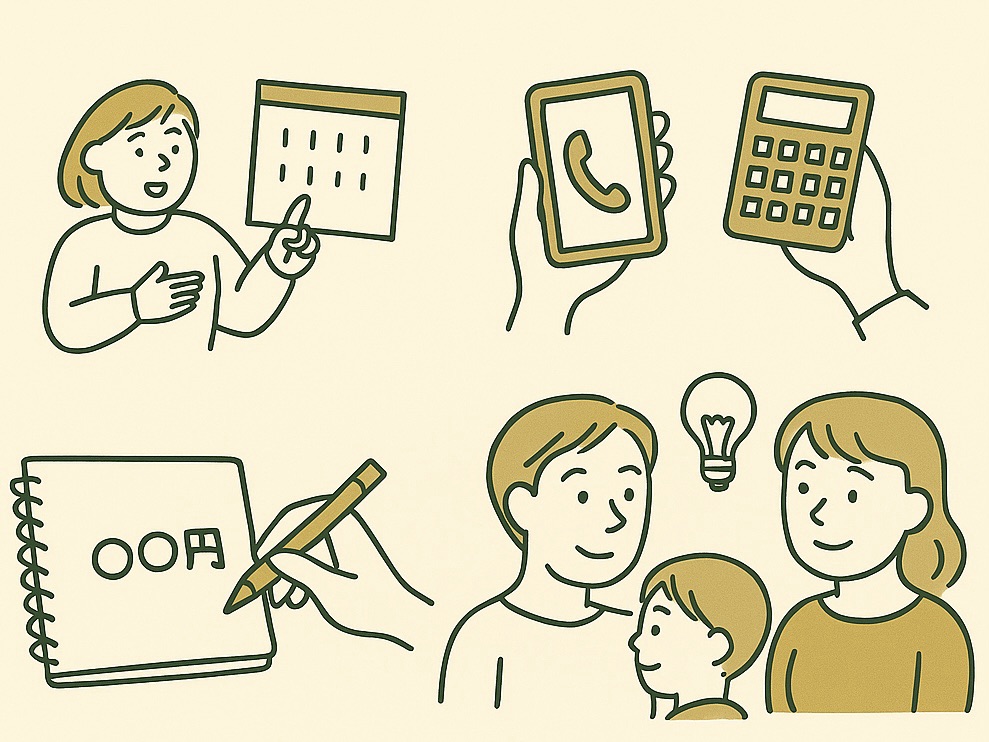
• 完璧を目指さず“ゆるく・長く”
• 固定費の見直し→日常のクセづけ→制度の活用 の順に着手
• 節約額を「可視化・言語化」して実感する(「今月は通信費-3,000円」など)
• “頑張りすぎない”のが一番続く
• 夫婦・家族で協力&情報共有を(片方だけの努力にならないように)
まとめ:節約とは「我慢」ではなく「選ぶこと」
子育て中の節約は、我慢大会ではありません。
「今はこれでいい」と選ぶ力を育て、
「将来に向けて今できること」を積み重ねるもの。
家庭によって使える制度も家計のクセも違います。
だからこそ、自分たちの目的に合った節約スタイルを見つけて、
“ちょっとラクになる仕組み”をつくっていきましょう。
毎月1万円でもムダを減らせれば、1年で12万円のゆとりに。
それは旅行になるかもしれないし、子どもの学資かもしれない。
節約は、家族にとっての「未来の選択肢」を増やす手段です。

