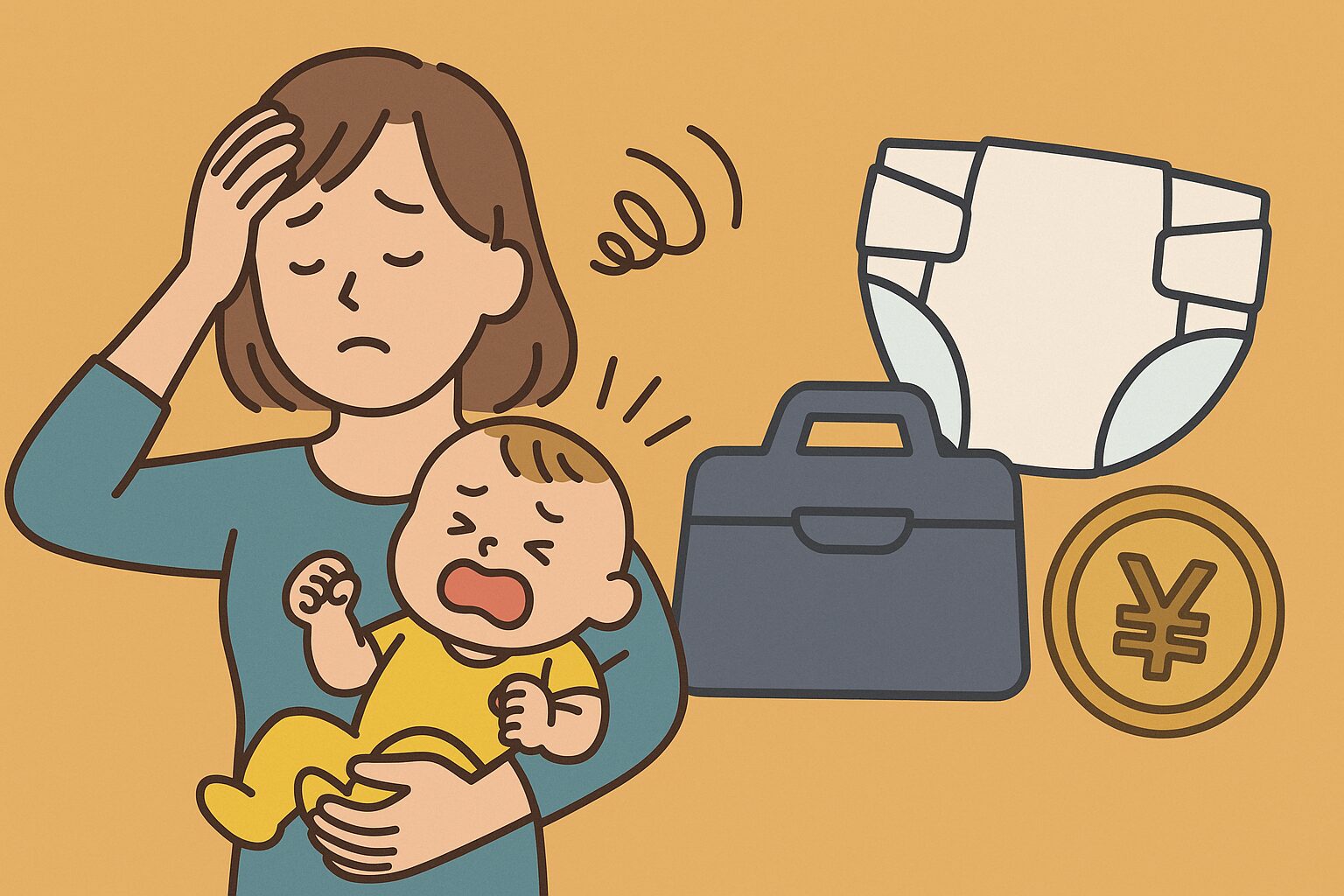「可愛いけど、正直しんどい」——
初めての育児が始まる0〜2歳。夜泣きに授乳、おむつ替えの毎日。さらに、ベビー用品にミルク代、保育園の費用…気づけば出費もどんどん増えていきます。
この時期の子育ては、心も体も財布もフル稼働。
この記事では、乳児期に本当にかかるお金の内訳から、保護者が感じやすいしんどさ、そして頼れる支援制度やリアルな家庭の声まで、まるごと解説します。
「これってうちだけ?」と思っているあなたにこそ読んでほしい、0〜2歳育児のリアルをお届けします。
目次
成長のスピードがすごい!乳児期(0〜2歳)の特徴とは

急速に変化する、身体・ことば・睡眠リズム
0〜2歳の乳児期は、赤ちゃんの成長がとにかくめざましい時期です。
生後すぐは授乳と睡眠の繰り返しで、1日の大半を寝て過ごしますが、月齢が進むと、首すわり(3〜4ヶ月)、寝返り(4〜5ヶ月)、お座り(6〜8ヶ月)、ハイハイ(8〜10ヶ月)、つかまり立ち(9〜11ヶ月)、そして1歳ごろには歩き始める子も出てきます。
言葉の発達も興味深い変化がたくさんあります。最初は「あー」「うー」などの喃語(なんご)から始まり、1歳頃には「ママ」「ブーブ」などの簡単な単語を発し、2歳になると「ママ、きた」などの二語文を使うようになります。
睡眠パターンも変化します。新生児期は3〜4時間おきの授乳で細切れ睡眠になりますが、3〜6ヶ月頃には夜にまとめて眠れるようになり、1歳を過ぎると夜間にまとまって寝る子も増えてきます。
それでも夜泣きやおむつ替えなどで、保護者は何度も起こされる日々が続くことも。楽天インサイトの調査によると、0歳児育児中の保護者の6割以上が「1日4時間以下の睡眠」と回答しています。
▶︎参考:https://insight.rakuten.co.jp/report/20211021/
親の生活も一変!仕事・家事・睡眠…全部が変わる
赤ちゃんの成長に合わせて、保護者の生活も大きく変わります。
特に初めての育児では「なにが正解かわからない」「想像以上に大変…」と戸惑うことが多いものです。
夜泣き、授乳、家事との両立、ワンオペ育児…。生活リズムは赤ちゃん中心になり、自分の時間は激減。慣れない中での毎日は、想像以上に体力とメンタルの消耗があります。
また、母親は育休・産休中で家にいることが多い一方、父親は仕事が忙しくてなかなか育児に関われない…というギャップに悩む家庭も少なくありません。
「夫婦の役割分担がうまくいかず、モヤモヤした」「自分ばかり大変に感じてしまった」など、すれ違いから産後クライシスに発展するケースも。
初めての育児に「これって普通?」という不安がいっぱい
最初の1〜2年は、すべてが初体験の連続。だからこそ、いろんなことが「これって普通?」「大丈夫かな?」と不安になりがちです。
他の子より成長が遅れてる? 授乳がうまくいかない… 寝てくれない・泣き止まない ちゃんと母親・父親になれてるのかな?
特に今は核家族が増え、実家も遠方にある家庭が多く、気軽に相談できる人がいない…という孤立感を抱える人も少なくありません。
だからこそ、自治体の子育て支援センターやママパパ向けの交流会、SNSや育児アプリの活用など、外とのつながりを持つことがとても大切です。
乳児期の子育ては、うれしさも大変さも一緒にやってくる、まさに“ジェットコースター”のような日々です。
でも、どんなママ・パパも「みんな最初は初心者」。うまくいかなくて当然です。
次章では、そんな乳児期に「実際いくらかかるの?」というお金のリアルに迫っていきます。
0〜2歳にかかるお金ってどれくらい?
乳児期の子育てには、喜びとともに“お金”の悩みもつきものです。
0〜2歳の育児では、初期のベビーグッズから日々の消耗品、保育料、医療費、そして行事など…想像以上に出費がかさみます。
この章では、そんな乳児期の支出を内訳ごとにわかりやすく紹介していきます。
初期費用(育児用品・ベビーグッズ)
赤ちゃんを迎えるための準備として必要なのが、育児用品の数々。
ベビーベッド(1〜3万円) ベビーカー(2〜5万円) チャイルドシート(2〜5万円) 抱っこ紐、バウンサー、肌着・衣類・おくるみ など
これらを新品で一通り揃えると、出産準備費用だけで20〜30万円程度かかることも珍しくありません。
お下がりをもらったり、フリマアプリや中古ショップを活用することで費用を抑える家庭も増えています。
毎月の消耗品(おむつ・ミルク・日用品)
紙おむつ:月6,000〜9,000円(1日8〜12枚×1枚20円前後) 粉ミルク:完全ミルクなら月8,000〜12,000円(母乳混合なら半分以下に) その他:おしりふき、スキンケア、洗剤、哺乳瓶、除菌グッズなど
これら日用品の合計で、月1万〜2万円程度の支出が平均的です。
▶︎参考:https://www.mamapicks.jp/archives/51928261.html
離乳食が始まると、ベビーフードや食材費も少しずつ加わってきます。
保育料のリアル(自宅保育 vs 認可・無認可)
育休が終わって仕事復帰する場合、多くの家庭が保育園を利用します。
認可保育園:月2〜5万円(世帯年収に応じて) 認可外保育園:月3〜7万円以上もあり(地域差あり)
東京都など都市部では月8万円近くかかるケースもあります。
逆に自宅保育の場合、保育料はかかりませんが、収入の減少や家事負担が大きくなります。
また、「保育の無償化」により、0〜2歳も住民税非課税世帯なら保育料が無料になる場合があります。
▶︎参考:https://www.youhomedeco.jp/blog/entry-186.html
医療費・予防接種・健診など
乳児期は定期健診や予防接種が多い時期です。
定期接種(四種混合・BCGなど):公費で無料 任意接種(ロタウイルスなど):自己負担あり(1〜2万円ほど)
医療費については、自治体の「乳幼児医療費助成制度」により、ほとんどの地域で0〜2歳児は自己負担が無料または1回200円程度です。
▶︎参考(東京都江戸川区)https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e036/kosodate/iryo/iryo/hospital.html
お祝い行事(初節句・1歳誕生日など)
乳児期には、次のようなイベントが続きます。
お宮参り(生後1ヶ月) お食い初め(100日祝い) 初節句(ひな祭り・こどもの日) ハーフバースデー 1歳の誕生日
衣装代、記念写真、会食費、お祝い膳などを含めると、1イベントあたり1〜5万円程度かかる家庭が多いです。
▶︎参考:https://www.hinamatsuri-iroha.com/shussei-iroha/hajizesshuku/
祖父母からのプレゼントやお祝い金でカバーできることもありますが、記念にアルバムや動画を作るなど、こだわりがあると費用はさらにアップします。
ざっくり総額まとめ
内閣府の調査によると、0〜2歳児を育てる家庭では、年間で平均約90〜100万円前後の子育て費用がかかっていると報告されています。
初期費用:約20〜30万円(1回のみ) 毎月の生活費:5万〜8万円前後 保育料(利用者のみ):月2〜8万円前後 医療費:ほぼ無料〜ごく軽微 行事・イベント費:年に数万円
もちろん、生活スタイルや支援制度の利用状況、お下がりや育休の有無などで出費は大きく変わりますが、「月に5〜8万円はかかる」と考えておくと現実的です。
▶︎参考:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/research/cost_of_child/cost_of_child.html
次章では、「育児がしんどい」と言われる理由に深く迫っていきます。夜泣き、孤独、保活…親たちのリアルな悩みに焦点を当てていきます。
「こんなに大変なんて…」0〜2歳育児のリアルな困りごと
乳児期の子育ては「幸せ」のイメージが先行しがちですが、実際には睡眠不足・保活・孤独感など、保護者が直面する“しんどさ”もたくさんあります。
ここでは、0〜2歳育児におけるリアルな困りごとや社会的課題をまとめます。
寝られない、休めない…睡眠不足と夜泣きの連続
「0〜2歳で一番しんどかったことは?」という質問で、ほぼ必ず出てくるのが夜泣き・授乳・寝かしつけ。
「夜中に何度も起こされて、まとまって寝られない」 「寝たと思ってもすぐ泣く」 「母乳で授乳間隔が短く、昼も夜も自分の時間がない」
こうした声が非常に多く寄せられます。
楽天インサイトの調査では、0歳児育児中の保護者の6割以上が1日4時間以下の睡眠と回答しています。
▶︎参考:https://insight.rakuten.co.jp/report/20211021/
また、母乳育児ならではの負担も。乳腺炎や食事制限、授乳間隔の短さなど、身体的にも精神的にも負担が大きい時期です。
保活と仕事復帰のリアルな壁
育休明けの仕事復帰を目指しても、希望通りに保育園に入れない=保活の壁にぶつかる家庭は少なくありません。
特に1歳児クラスは倍率が高く、都市部では希望園すべて落ちるケースも。
2023年4月時点の全国待機児童数は2,680人 その約85%が0〜2歳の低年齢児
▶︎参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33624.html
希望の時期に保育園が決まらなければ、育休延長や退職の選択を迫られることもあります。
しかも育休中は育児休業給付金で収入が手取りの67〜50%に減るため、家計にも大きな影響が。
「もう少し子どもと過ごしたい気持ち」と「生活のために復帰しなければならない現実」に悩む人も多いです。
ワンオペ・孤独・育児ストレスと夫婦のすれ違い
実家が遠方で頼れない、パートナーの帰宅が遅いなどの理由で、一人で育児を担う“ワンオペ状態”になる保護者は少なくありません。
「昼も夜も赤ちゃんと二人きり」 「自分だけが大変で誰にも相談できない」 「夫は仕事で疲れてるからと頼れず…」
こうした状況から、孤独感や育児ストレスを強く感じる人も多く、産後うつや夫婦不和(産後クライシス)へつながることも。
NHKの調査では、「母親の約1割がほぼ一人で育児をしている」というデータもあります。
▶︎参考:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230209/k10013975941000.html
夫婦で家事・育児をどう分担するか、話し合いの機会をもつことが重要です。
保育園に入れない“保活格差”も
待機児童問題は改善傾向にあるものの、地域差は大きく、東京都など都市部ではまだ入園が難しいエリアもあります。
2024年4月時点の厚労省発表では、全国の待機児童数は過去最少の2,567人ですが、人気の園は依然として高倍率。
▶︎参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37447.html
やむを得ず認可外保育園やベビーシッターを選ぶ家庭もありますが、費用負担が重く、
「月8万円以上の保育料は家計的にきつい」 「預け先が見つからず、仕事を辞めざるを得なかった」
という声も。
保活の結果次第で生活やキャリアが大きく左右されるという現実に、ストレスを感じる家庭も少なくありません。
0〜2歳の育児は、赤ちゃんの成長の嬉しさと同時に、親の生活・働き方・夫婦関係に大きな影響をもたらす時期です。
だからこそ、ひとりで抱え込まずに、周囲の支援や制度を活用することが大切。次章では、頼れる支援制度・使えるサービスをまとめてご紹介します。
知ってると助かる!使える支援制度まとめ

乳児期の子育ては、ただでさえ出費や負担が多い時期。でも実は、経済的・心理的なサポートになる公的制度や地域の支援がいくつも用意されています。
ここでは、0〜2歳の育児家庭が活用できる代表的な制度やサービスをわかりやすくまとめました。
児童手当(2024年から拡充)
子どもがいる家庭に支給される手当です。
2024年10月からは対象年齢が高校卒業相当(18歳)まで拡大、所得制限も撤廃されます。
0〜3歳未満:月15,000円 3歳〜18歳:月10,000円(第3子以降は月30,000円)
支給は年3回に分けて行われます。申請は市区町村の窓口へ。
▶︎参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo_teate.html
育児休業給付金(パパもOK!)
雇用保険に加入している人が育休を取った場合に支給される給付金です。
育休開始〜180日目:賃金の67% 181日目以降:賃金の50%
支給期間は原則子が1歳まで。ただし保育園に入れなかった場合など、2歳まで延長可能です。
2022年からは「産後パパ育休」制度もスタートし、パパが出生直後に最大4週間休める仕組みが整備されました。
さらに2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が新設され、夫婦ともに育休を取得すれば、最大で賃金の80%相当(実質ほぼ手取り全額)が支給される新制度も始まる予定です。
▶︎参考:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001461102.pdf
▶︎参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_ikuji.html
幼児教育・保育の無償化
2019年10月からスタートした「保育の無償化」制度。
3〜5歳児:すべての子どもが対象(認可園は原則無料) 0〜2歳児:住民税非課税世帯のみ対象(月額上限あり)
無償化の対象は「保育料」のみで、給食の食材費・行事費・おむつ代などは自己負担です。
▶︎参考:https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/gaiyou.pdf
医療費助成制度(子ども医療費の無料化)
多くの自治体で、子どもの医療費(保険診療分)を公費でカバーする制度があります。
たとえば東京都江戸川区では高校3年生相当まで通院・入院ともに自己負担ゼロ。
▶︎参考(江戸川区):https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e036/kosodate/iryo/iryo/hospital.html
横浜市でも2023年8月から中3まで所得制限なしで医療費が無料になりました。
▶︎参考(横浜市):https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/iryo/iryo/iryojosei/jidou/iryojosei.html
地域によって制度が異なるため、必ずお住まいの自治体のホームページを確認しましょう。
子育て支援センター・一時預かりサービス
「家で赤ちゃんとずっと二人きり」「話し相手がいない」
そんなときに頼りになるのが、各自治体が設置している子育て支援センターです。
保育士や相談員が常駐していて気軽に相談できる 同じ年頃の親子とふれ合える 無料で遊べるスペースやイベントがある
また、短時間だけ子どもを預けられる一時預かりサービスも便利。
リフレッシュ、通院、急な用事のときに使える心強い制度です。
利用料金は自治体によりますが、1時間数百円〜が多く、事前予約が必要な場合があるため確認しておきましょう。
その他:地域ごとの独自支援や企業サポートも
自治体によっては、以下のような独自の育児支援を行っているところもあります。
出産祝い金や育児用品購入券の配布 子育て家庭向けの住宅補助制度 多胎児(双子・三つ子)向け支援 家庭訪問型サポート(ホームスタート等)
また、企業によってはベビー用品の社員割引、在宅勤務や時短勤務の選択肢を用意している場合もあります。
「知らなかった」で損をしないために、育児が始まる前から地域の制度やサービスをチェックしておくことが大切です。
自治体の広報誌、母子手帳に挟まれた案内、公式サイトなどを定期的に確認して、使える支援は遠慮なく活用していきましょう。
次章では、そんな支援制度の中でも「使ってよかった!」「救われた!」というリアルな声やエピソードをご紹介します。
先輩ママ・パパのリアルボイス

ここまで、乳児期にかかるお金や困りごと、使える制度をご紹介してきましたが、やっぱり気になるのは「実際の家庭はどう乗り越えてるの?」というリアルな声ですよね。
この章では、0〜2歳の育児を経験した先輩ママ・パパたちの体験談を紹介します。苦労したこと、助けられた制度、嬉しかった瞬間…。共感できるエピソードがきっと見つかるはずです。
「思ったよりお金かかる!」リアルな費用感覚
ある共働き家庭(都内在住)は、出産準備や産後グッズに約30〜40万円を使い、育休明けに保育園に預けると月5万円の保育料が家計を直撃。
「夫婦で数万円ずつの負担増。想定してたけど、やっぱり重かったです…」
一方で、こんな工夫で費用を抑えた家庭も。
「お下がりやフリマアプリを活用して、初期費用を半分以下にできました」
「雛人形は祖父母が用意、お祝い膳は手作り。節目は大切に、でも無理しすぎずに」
「児童手当が日用品代の支えになった」「医療費が無料で本当に助かった」という声も多く、公的支援のありがたさを実感する家庭は多いようです。
「あの制度があって助かった!」と感じた瞬間
初めての育児では、誰かのサポートが本当に心の支えになります。
「実母が里帰り中に家事・育児をサポートしてくれた」 「義両親が週末に来てくれて、一人で休める時間が持てた」
地域のサポートに助けられたという声も多くありました。
「子育て支援センターで育児相談できて、ママ友もできた」
「誰にも会えずしんどかったけど、SNSで同じように頑張るママに励まされた」
また、2020〜2022年頃はコロナ禍の影響で両親学級や地域のイベントが中止になるケースも多く、「孤独感」を強く感じたという声も。
「誰とも話さず1日が終わる日が続き、不安で泣いたこともあります」
「でも、オンラインで相談できる窓口や育児コミュニティに救われました」
「やっぱり夜が一番きつかった…」しんどかったことと乗り越え方
多くの家庭が口をそろえて言うのが「夜がしんどい」ということ。
「2時間おきの授乳で、自分がいつ寝たかもわからなかった」 「寝かしつけに2時間かかって、ようやく寝たと思ったらまた起きる」
「体調が悪くても休めない。ワンオペ育児で限界を感じた」
「夫も仕事で疲れていて、言いづらくて全部一人で抱えてた」
でも、どの家庭も試行錯誤しながら乗り越えているのも事実です。
「昼寝中に一緒に寝て回復するようにした」 「週末は夫に丸投げして、1人で寝かせてもらう日を作った」 「寝かしつけのドライブが唯一の休憩時間だった」
そして共通していたのが、こんな気持ち。
「“ママ”って呼ばれた瞬間、すべてが報われた」
「最初の笑顔、最初の“歩いた!”…疲れなんて一瞬で吹き飛びます」
最後に:大変だけど、かけがえのない時間だから
乳児期の子育ては、泣きたいほど大変な時もあります。
でも、それ以上に子どもの成長は愛しく、何にも代えがたい喜びです。
「完璧じゃなくていい」 「助けを求めてもいい」 「ひとりじゃない」
そう思えるだけで、ちょっと心が軽くなりますよね。
子育ては、家族と地域と社会みんなで支えるもの。
一人で頑張らず、使える制度やサービスを味方にしながら、“その子としか過ごせないこの瞬間”を大切に過ごしていきましょう。